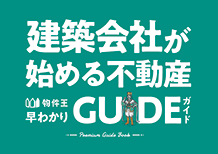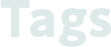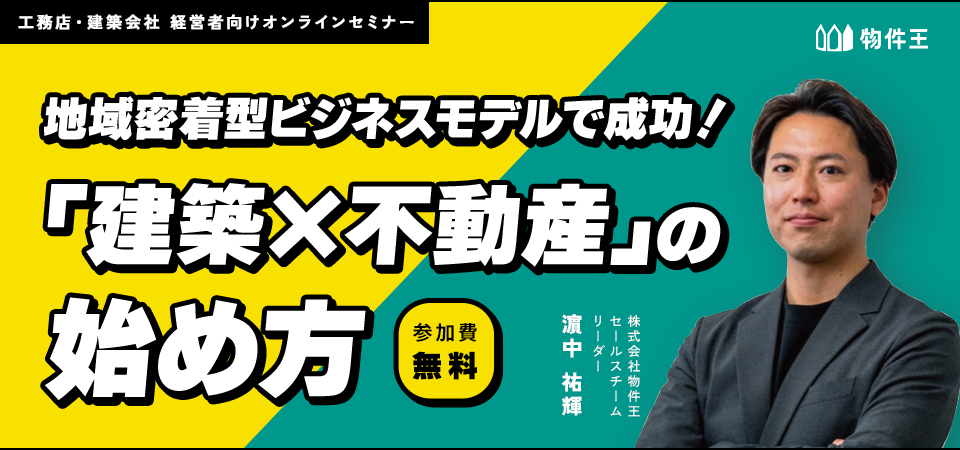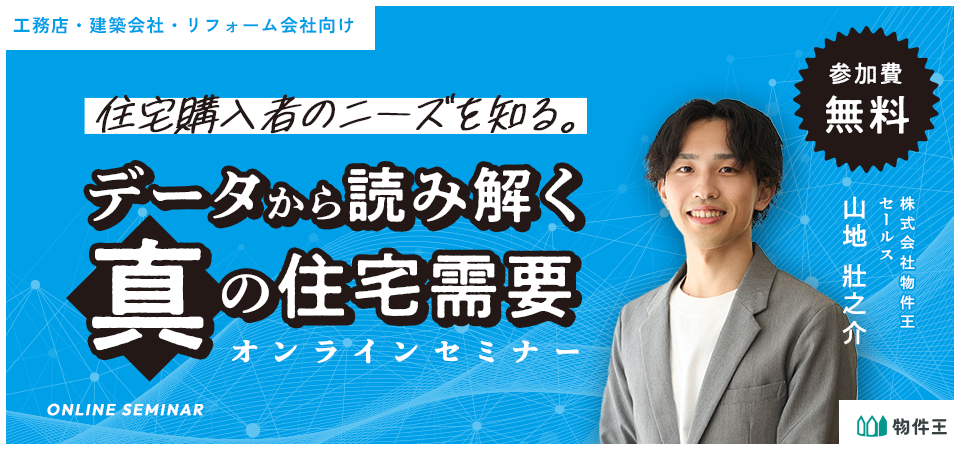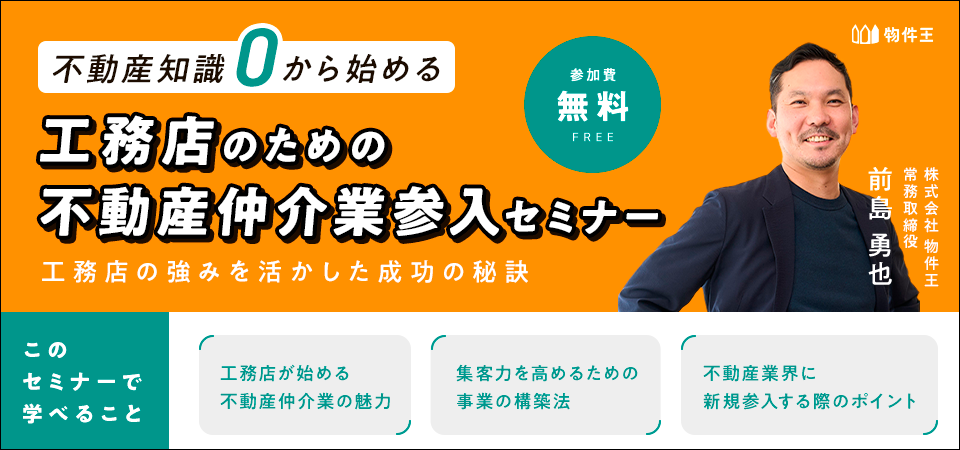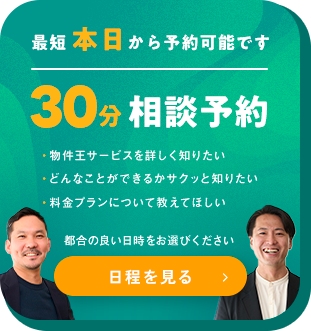今回は第2回目として、中古マンションで意外と起こりがちなトラブル事例を取り上げます。
【相談事例】中古マンションで光回線不可…仲介業者は費用負担すべきか?
Q:決済後に「光回線が利用できない」ことが判明しました。仲介業者として費用を負担すべきでしょうか?
A:まずは、どのような説明を行い、どのような前提で購入した物件かによって大きく結論が変わります。本相談では、「光回線が利用できる」と説明した事案だったので、設置費用と利用費用の差額を一定期間補填する対応が、法的にも実務的にも妥当と考えられます。
相談背景
ある中古マンションの取引で、仲介会社は「光回線が利用できる」と説明して売買契約を締結しました。
ところが決済後に判明したのは、実際には各部屋には光ファイバーが引き込まれておらず、既存電話線を利用するVDSL方式でしか利用できないこと。しかも利用ポートはすでに満杯で、新規契約は当面できない状態でした。
買主は当面の代替策としてホームWi-Fiを利用中で、設置費用や月額費用は仲介会社が負担する方向で合意を検討しています。ただし、光回線が利用可能になる時期が不透明で、どの程度の期間を補填すべきかが悩ましいところでした。
幸い感情的なトラブルには至っていませんが、今後の対応次第ではクレームや紛争化の可能性もあるため、慎重な判断が求めらるため、弁護士に相談する流れとなりました。
弁護士の回答
1.契約解除は難しい理由
まず、光回線が利用できないという事実だけで売買契約の解除が認められる可能性は低いと考えられます。なぜなら、住居としての本質的機能――すなわち「居住が可能かどうか」には直結しないからです。
例えば雨漏りやシロアリ被害といった深刻な欠陥であれば契約不適合により解除が認められる余地がありますが、インターネット回線は居住の利便性に影響するにとどまります。代替手段としてモバイルWi-Fiやホームルーターが存在することも、解除を認めにくい理由の一つです。
2.参考になる裁判例
インターネット回線に関する裁判例は現時点で見当たらないように思います。しかし、類似する事例としてテレビの電波障害を巡る裁判があります。平成4年頃の事案では、NHKなどがゴースト障害で視聴困難となったケースにおいて「アンテナ設置費用+ケーブルテレビ10年分の利用料相当」を損害と認めた判決がありました。
もっとも、テレビ放送は公共電波で無料で受信できる一方、光回線は利用料を支払って契約するものである点が異なります。そのため裁判例をそのまま援用することはできませんが、補償額を考える上での参考材料にはなります。
3.仲介会社の説明義務と責任範囲
仲介会社には、買主が購入の判断を誤らないよう正確な情報を提供する説明義務があります。特に広告や重要事項説明書に「光回線利用可」と記載する場合、単に建物まで光回線が来ているという意味ではなく、実際に各住戸で契約可能かどうかまで確認する必要があります。
今回のように「光回線可」と説明していたのに、実際にはVDSL方式でしか利用できず、しかもポートが空いていないという状況は、説明義務違反を指摘されても仕方がありません。ただし、マンションの設備や管理組合の判断に左右される部分も多いため、仲介会社がすべての責任を負うわけではなく、対応は「誠実さ」と「合理性」のバランスが重要です。
現に単に「光回線が利用できる」と説明したかだけではなく、「なぜ利用できなくなったのか」というのが、単なる仲介会社の落ち度なのか、建物特有の技術的な事情によるものなのかなど、現実的には複雑な問題が影響します。
4.実務的に妥当な補償額の考え方
今回は、仲介会社側が落ち度を認めた前提ですので、補償の内容としては、まず代替手段の初期費用(約3万円程度の設置費用)は全額負担するのが妥当かと考えました。
次に月額費用の補填についてですが、基準となるのは「光回線を利用できた場合に支払う利用料との差額」です。例えば光回線の月額が5,000円程度であり、ホームWi-Fiが同額かやや高い程度なら、その差額分を補填する考え方です。
期間については、テレビ電波障害の裁判例では「10年」とされたものの、光回線の場合は将来的に改善工事が行われる可能性もあるため、そこまで長期を前提とする必要はないと思います。実務的には「3〜5年程度」を上限とし、補填期間中に光回線が利用可能になった場合には補填を終了する、という合意が合理的です。
5.まとめ
光回線が使えないこと自体は契約解除の理由にはなりにくいものの、仲介会社の説明が不十分であれば一定の補償を行う必要があります。
対応としては「設置費用の全額負担+利用料差額の補填(3〜5年)」を目安に交渉するのが妥当であり、買主と誠実に話し合うことでトラブル化を防ぐことができるといえるでしょう。
弁護士の実務コメント
インターネット回線は今や生活必需品に近く、その重要性は年々高まっています。判例は少ない分野ですが、今後はトラブル事例も増えていく可能性があります。
仲介実務では「光回線可」と断定的に説明するのではなく、利用方式やポート空き状況まで確認する姿勢が欠かせません。
本来仲介会社としては、建物状況等によっては利用できない可能性がある、などの不測のリスクを踏まえた重要事項説明などの対応も必要かもしれません。
ネット回線関係は、かなり技術的にも難しく、仲介会社としても可能な範囲で確認していくほかありません。
もっとも、今回のように落ち度を認めて、誠実に補償を提案することは、コンプライアンス対応としても高く評価されるものといえるでしょう。
---
山村先生、ありがとうございました。
今回の事例は、お客様の快適な暮らしを左右する、まさに現代ならではのトラブルと言えるでしょう。
特に、インターネット環境のような生活インフラに関わる事柄は、単に「契約不適合責任」の問題として片付けられない、複雑な背景を伴うケースが多々あります。
物件王では、このような複雑な事案にも対応できるよう、山村法律事務所との連携を通じて、加盟店の皆様を強力にサポートしてまいります。
法的な知識を身につけることは、トラブルを未然に防ぎ、お客様からの信頼を得る上で不可欠です。
今後も、皆様が安心して事業を進められるよう、実践的な情報を発信してまいりますので、次回の連載もどうぞご期待ください。

山村 暢彦氏
弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。
相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。
クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。
現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数7名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。
弁護士法人 山村法律事務所
神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階
電話番号 045-211-4275
神奈川県弁護士会 所属
山村法律事務所ウェブサイト
不動産・相続:https://fudousan-lawyer.jp/
企業法務 :https://yamamura-law.jp/