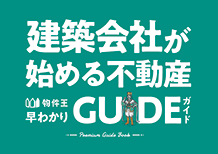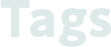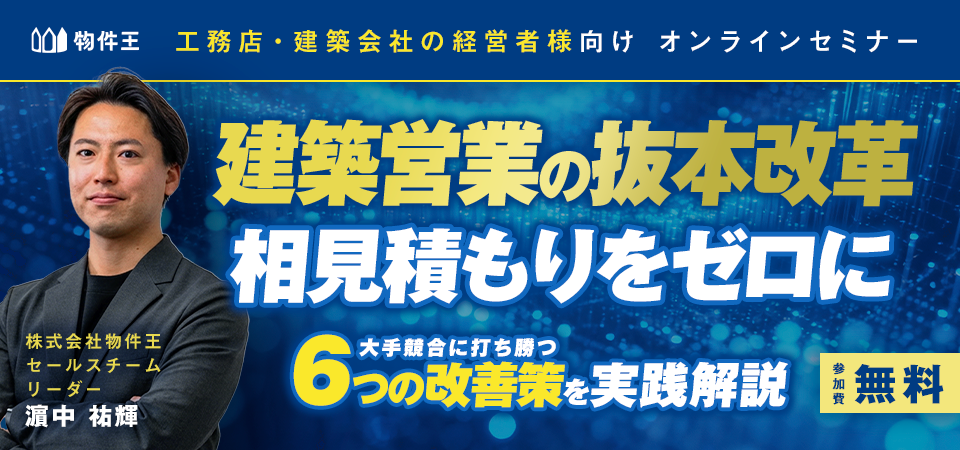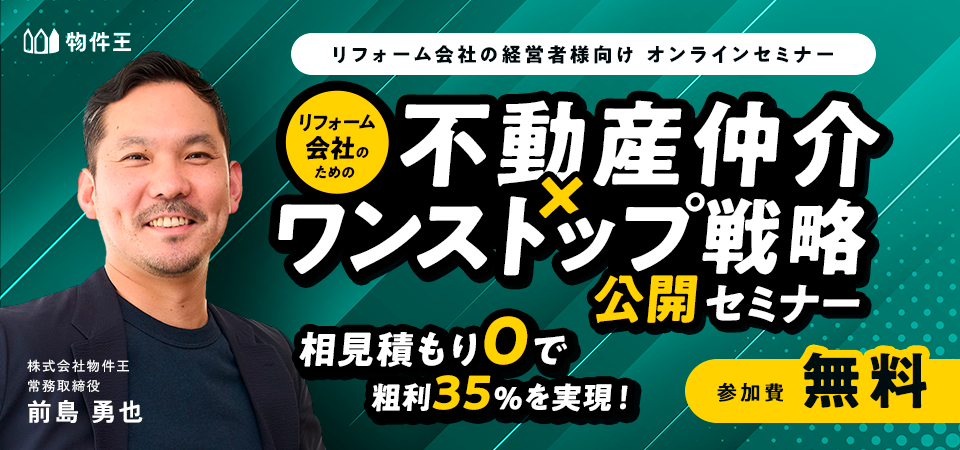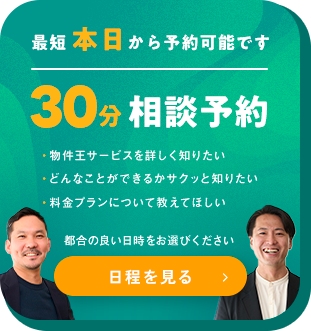今回は、弁護士が解説する「不動産業のよくある相談事例」シリーズ第3弾、中古戸建の売買で意外と見落としがちな落とし穴についてお話します。
買主が雨漏りを「了承済み」で物件を購入する場合でも、売主である宅建業者は責任を問われるのでしょうか? 結論から言うと、「了承済」という合意だけでは、契約不適合責任を免れるのは難しいのが実情です。
この複雑な問題を、実際の相談事例を交えながら、わかりやすく紐解いていきましょう。
Q: 買主が雨漏りを了承して中古戸建を購入する場合でも、宅建業者は契約不適合責任を免れることができますか?
A: 残念ながら宅建業法40条の強行規定があるため、合意があっても免責は難しく、「古家付土地」として売却する方法などを検討すべきです。
相談背景
ある不動産会社が中古戸建を買い取り、解体して土地として販売する予定でした。ところが販売準備の途中で、ある買主から「建物ごと購入したい」との申し出がありました。
問題は、この建物について前所有者から「大雨の際に増築部分で雨漏りがある」との告知を受けていた点です。
修繕は難しく、売主として現状のまま引き渡すことを検討しましたが、宅建業法の契約不適合責任との関係が不安要素となりました。
仲介担当者としては、買主が了承している以上問題はないのか、それとも業者の責任が残るのか、判断に迷い、弁護士に相談を寄せた事例です。
契約不適合責任の基本と「合意の効力」
契約不適合責任とは、引き渡された目的物が契約の内容に適合していない場合に売主が負う責任をいいます。
ここで重要なのは「契約内容」です。例えば、一般の売主・買主間で「雨漏りあり」と明記した建物を売買した場合、実際に雨漏りしてもそれは契約どおりであり、契約不適合には該当しません。言い換えれば、「ジャンク品としてのパソコン」を買う場合と同じで、壊れていることが前提になっている以上、動作しなくても責任追及はできないのです。
民法上は当事者の合意が基準となるため、通常の個人間売買であれば、買主が了承した欠陥について売主は責任を負わないのが原則です。
宅建業者の場合と宅建業法40条の強行規定
ところが売主が宅建業者の場合は事情が大きく変わります。宅建業法40条は、宅建業者が売主となる場合に、買主に不利な特約を原則として無効とする強行規定を置いています。
具体的には「契約不適合責任を負わない」という免責条項は、宅建業者には認められません。つまり「雨漏りがあることを承知で買います」という合意があったとしても、当事者の合意よりも強行法規である宅建業法40条が優先されます。
ここに、「合意の効力」と「法律の強行規定」の衝突が生じるわけです。
令和4年裁判例が示した免責特約の無効
実際に令和4年の裁判例では、築古物件について「水道設備が老朽化しており、赤水が出る・故障する可能性がある」ということを前提に売買が行われました。
売買契約では「この点について、売主は責任を負わない」とする特約が定められていましたが、裁判所は宅建業法40条を根拠にこの免責条項を無効と判断しました。つまり、買主が古さを承知して購入していたとしても、「契約不適合責任を免れる」との特約は宅建業者にとって通用しなかったのです。
この裁判例は、「買主の合意があっても、宅建業者の責任は残る」という実務上の厳しさを象徴するものといえます。
(※ただし、赤水の程度がわずかで、水道設備そのものに不具合がないという認定で、特約は否定しましたが、裁判結果自体は、買主敗訴の結論となりました。)
本件での対応策と実務的な工夫
本件でも、買主が雨漏りを了承しているからといって、中古戸建としてそのまま売却すれば宅建業法40条に抵触する可能性が高いと考えられます。
免責特約を設けても無効とされるリスクが強いため、実務的には「古家付土地」として売却する方法が現実的です。
つまり、建物を売買の対象から外し、あくまで土地を購入してもらう形をとるのです。そのうえで、建物を解体せずに残したまま引き渡し、買主が自らの責任で利用を続けることは可能です。
これにより、売主は建物の欠陥について契約不適合責任を追及されるリスクを大幅に回避できます。
他に、決済前に買主自身が修繕する、といった方法も理論的には考えられますが、法的リスクや現実性の点で採用されにくいのが実情です。
まとめ
契約不適合責任は「当事者の合意内容に適合しているか否か」で判断されるため、一般の売主・買主であれば「雨漏りあり」として売買すれば責任は問われません。
しかし宅建業者が売主の場合、宅建業法40条が強行規定として働き、合意による免責は無効となるリスクが高いのが現実です。
令和4年の裁判例もその傾向を裏付けています。したがって、実務では「古家付土地」として売却する方法を検討し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
弁護士の実務コメント
宅建業者が売主となる場合、買主との合意よりも宅建業法40条を優先するのが裁判所の基本姿勢です。
雨漏りのように居住性の根幹に関わる欠陥については、免責特約が無効と判断されやすいでしょう。仲介の現場では「了承済みだから大丈夫」と考えず、今回のようなケースでは「古家付土地」という形で売却し、責任範囲を整理することが実務的には比較的安全といえるでしょう。
ただ、実務的には「経年劣化のため、経年劣化を前提とした設備、建物です。」という特約は普及しており、実際には、経年劣化により軽微な設備不良等は買主側から契約不適合責任を請求できない結果となることもあります。
そうすると、「宅建業法40条違反になる契約不適合免責になる内容なのか」「経年劣化等の理由により有効であり、買主側に契約不適合責任を請求できないようにする特約なのか」というのが、その内容や建物利用における重要度によって変わってくるケースがあると言えます。
特約の作成の仕方によって有効無効が変わってくるケースもあるので、老朽化建物の特約作成はなかなか気を遣う作業だなと改めて実感します。
いかがでしたでしょうか?
一見すると買主が納得しているから大丈夫だと思われがちなケースでも、宅建業法によって責任が免れない厳しい現実があることがわかりました。
不動産取引は、専門知識が求められる場面が多々あります。お客様との信頼関係を築くためにも、トラブルを未然に防ぐ知識をしっかりと身につけておくことが大切です。
これからも、不動産業に携わる皆さまが安心して業務に取り組めるよう、実務に役立つ情報をお届けしていきますので、どうぞご期待ください。

山村 暢彦氏
弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。
相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。
クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。
現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数7名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。
弁護士法人 山村法律事務所
神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階
電話番号 045-211-4275
神奈川県弁護士会 所属
山村法律事務所ウェブサイト
不動産・相続
企業法務