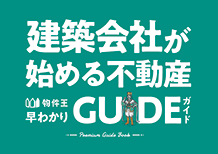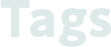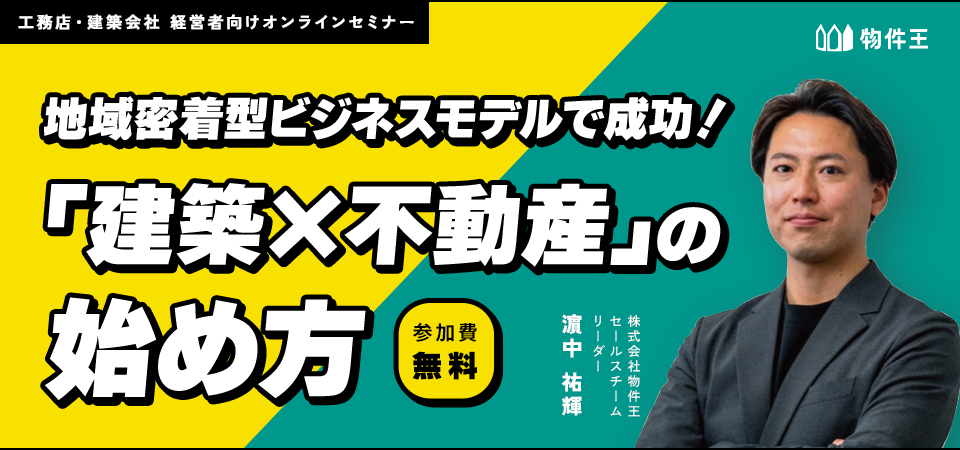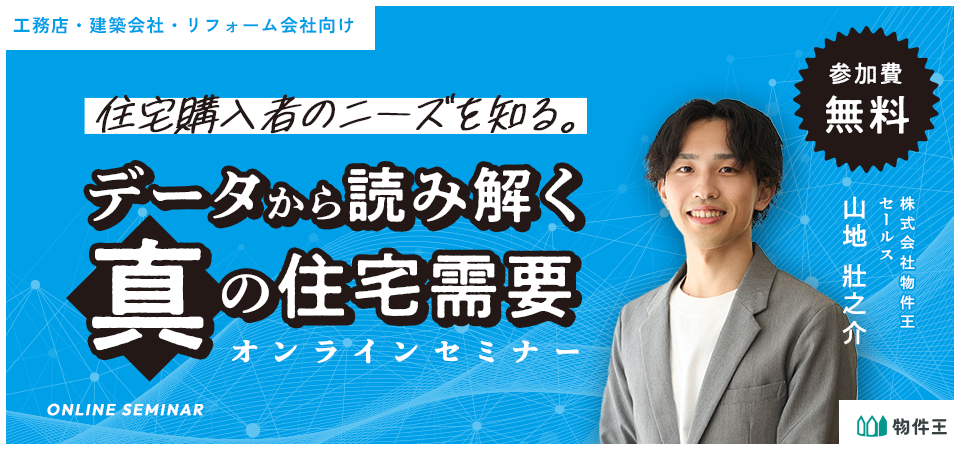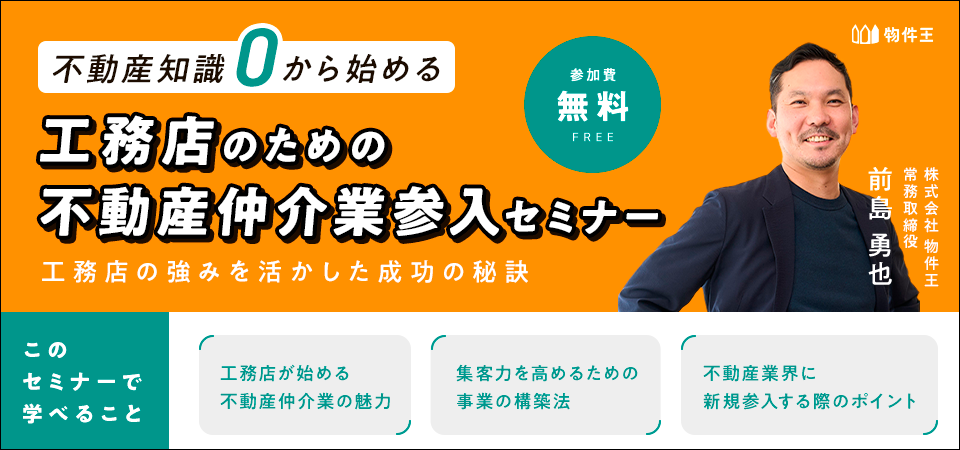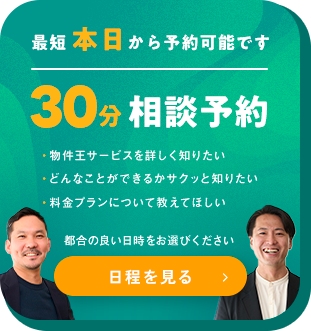今回は、弁護士が解説する不動産業のよくある相談事例、土地取引における「地盤・地中障害物」に関するトラブルを取り上げます。
買主様から「地盤保証が受けられない」「地中にガラが見つかった」といった相談が寄せられた際、仲介業者や売主はどこまで責任を負う必要があるのでしょうか。法的に見て、それは契約不適合に該当するのでしょうか?
実際の相談事例をもとに、法的な判断基準と実務的な対応策を解説します。
Q: 土地を引き渡された後の地盤調査で「地盤保証が受けられない」と判明しました。この場合、契約不適合にあたるのでしょうか?また、地中にガラが多く見つかった場合、撤去費用を売主に請求できますか?
A: 建築自体が可能であれば、原則として契約不適合にはあたりません。ただし、地中のガラが自然石ではなく建築廃材などの場合には、撤去費用を請求できる可能性があります。
相談背景
宅建業者が造成した土地を一般消費者が購入し、仲介会社が両手で取引を担当した事例です。
もともと畑だった土地を造成後、売主が地盤調査を行い、脆弱との診断から柱状改良工事を実施しました。
そのうえで、建築可能との判断のもと売買契約が締結されました。ところが、引渡し後に買主が改めて地盤調査を依頼したところ、柱状改良箇所以外で杭が高止まりし、地盤保証の対象外と判断されました。
買主からは「保証が受けられないのは契約不適合ではないか」「地中にガラがあるなら売主負担で撤去できないか」との相談が寄せられ、仲介会社としての対応に苦慮しています。
弁護士の回答
1.地盤保証が受けられないだけでは契約不適合にあたらない理由
契約不適合は、契約の目的物が「通常有すべき品質・性能」を欠く場合に認められます。
本件のように、建築自体は可能であるにもかかわらず、地盤保証が受けられないという理由だけでは、土地としての基本的な機能が損なわれているとはいえません。
裁判実務でも「建築基準法上の基準を満たす建物が建てられれば不適合ではない」と判断される傾向にあります。
保証が受けられないという事実は、あくまで施工上の不利益にとどまり、法的には契約不適合に該当しないのが原則です。
2.契約条項や免責特約の影響
契約書上に「土地には大小様々な自然石が含まれる」といった免責条項がある場合、自然石や地中の岩石等については買主の承知事項とされ、売主の責任は否定されるのが通常です。
これにより、買主はある程度の地盤ばらつきを前提に購入していることになります。
したがって、仮に保証が受けられなくても、その原因が自然的要因に基づくものであれば、契約上の責任追及は困難といえます。
特約の文言は実務上非常に重要であり、売主側が宅建業者であっても、容認事項が明示されていれば責任は限定的に解されます。
3.仲介会社の説明義務・責任範囲
仲介会社には、既知の重要事項について買主に説明する義務があります。しかし、地盤保証の可否や改良工事の詳細は、専門的かつ施工段階で判明するといった要素が強く、仲介段階で確定的な判断をすることは難しいのが実情です。
したがって、改良工事が実施された経緯や、売主が提示する調査結果を適切に伝えていれば、仲介業者としての説明義務を果たしたといえます。
むしろ、買主に対して「保証が必ず受けられる」と断定的に説明してしまうと、誤認を招くリスクがあるため、表現には十分な注意が必要です。
4.実務的に可能な対応策
今回のようなケースでは、まず試掘によって実際の地中状況を確認することが重要です。
そのうえで、地中のガラが自然石系か人工廃材かを明確に区別します。自然石や造成残土であれば、特約により売主責任は免れますが、建築廃材など明らかに不適切なものが混入している場合には、売主に撤去費用の一部負担を求めることが可能です。
ただし、裁判での立証は困難なため、実務的には調査結果をもとに交渉し、売主の任意負担での和解的解決を目指すのが現実的な方向性です。
5.まとめ
地盤保証が受けられないことは、直ちに契約不適合とはいえません。土地としての利用が可能である限り、法的な追及は難しいのが実情です。
ただし、地中障害物の種類や影響によっては、一定の費用負担を求められる余地もあります。仲介会社としては、改良工事や特約内容を正確に把握し、買主にリスクを説明することが最も重要です。
説明の一言が、後のトラブル防止につながります。
弁護士の実務コメント
地盤に関するトラブルは、費用対効果の観点から裁判提起が難しく、仮に裁判になっても「契約不適合が認められない」ケースが多いため、実務では補修・撤去費用を巡る交渉解決が中心となります。
仲介会社としては、契約前に改良履歴や特約内容を明示し、保証の有無を断定せずに説明する姿勢が求められます。
特に土地取引に慣れていない一般的な買主は、不動産が工業製品のように完璧な商品ではなく、後から不具合やリスクが生じる可能性があるという点を理解していないことが多いです。
そのため、仲介会社としては、不動産取引特有ともいえる「完璧な不動産が補償されるわけではない」という点を、しっかりと伝えておく必要があります。
小さな表現の違いや説明の有無が、後の責任分岐点となるため、事前説明を徹底する意識を持つことが大切です。
土地取引の地盤問題は、法的責任の所在が曖昧になりがちですが、今回の解説で「建築の可否」が判断の大きな分かれ目となることが明確になりました。
物件王では、加盟店の皆様が直面する専門性の高い法規的な課題に対し、実践的な解決策を提供してまいります。
リスクを理解し、正確に説明することが、トラブルを防ぐ最善策です。今後も、皆様の事業を力強くバックアップしてまいりますので、次回の連載にもご期待ください。

山村 暢彦氏
弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。
相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。
クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。
現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数7名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。
弁護士法人 山村法律事務所
神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階
電話番号 045-211-4275
神奈川県弁護士会 所属
山村法律事務所ウェブサイト
不動産・相続
企業法務