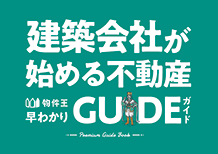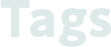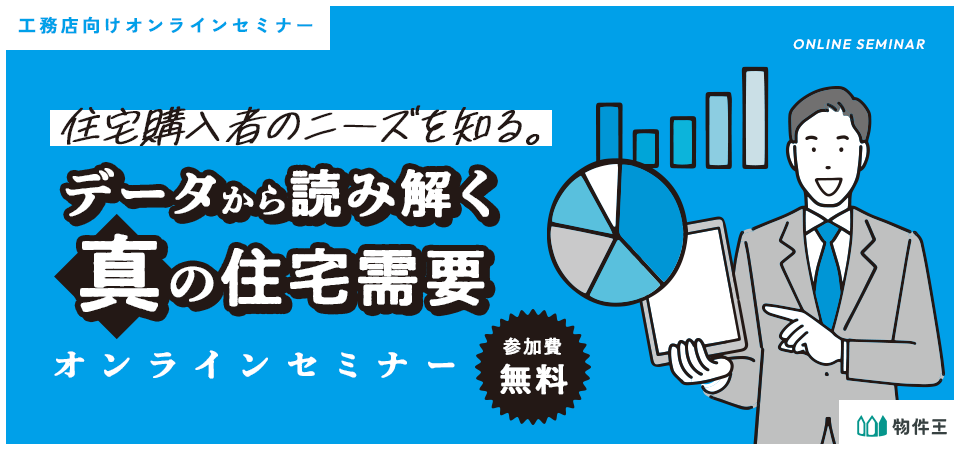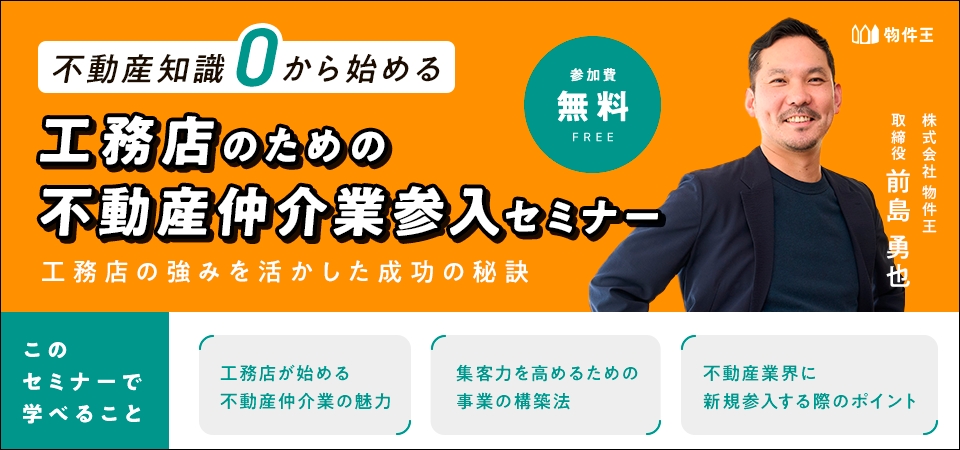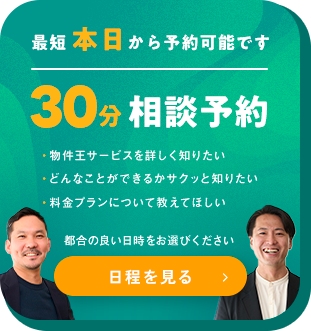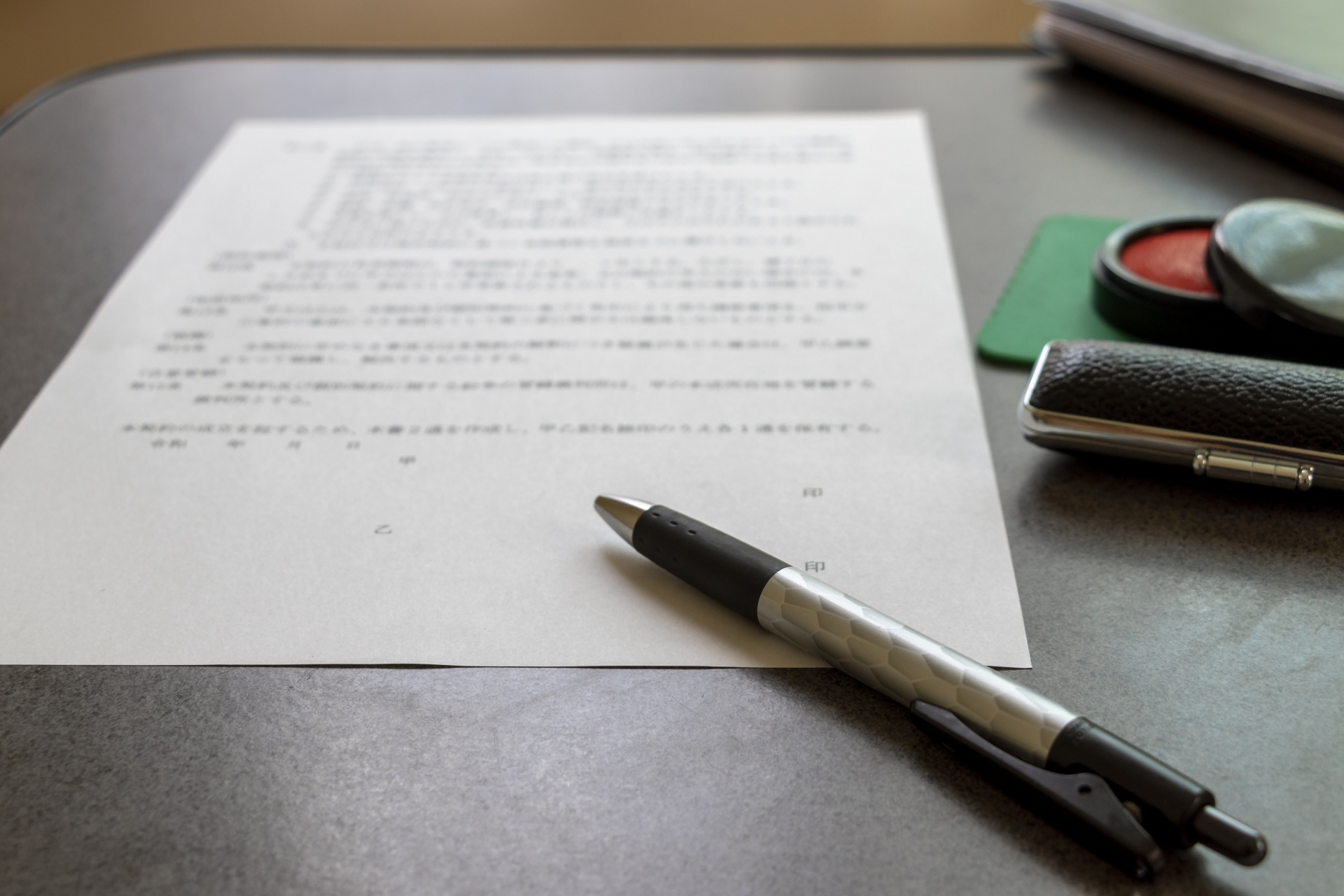
今回は、収益物件の取引において特に重要となる「融資特約」に関するトラブル事例を取り上げます。
収益アパートやマンションの購入では、融資条件(金利や期間)が、事業の収支計画や利回りに直結します。そのため、事前審査と本審査で条件が変わると、買主様にとっては致命的な問題となりかねません。
「融資が否認された場合」の解除は一般的ですが、「融資は承認されたものの、条件が悪化した」場合にも契約を解除できるのでしょうか?そして、仲介会社として、契約書でどのようにリスクを回避すべきでしょうか。
今回も、山村法律事務所 代表弁護士 山村 暢彦先生に、具体的な特約の記載方法や過去の裁判例を踏まえた対応策を解説していただきます。
目次
Q:融資特約の解除条件に「金利」や「融資期間」の変更も含めることは可能でしょうか?
A:はい、現実的かつ合理的な特約です。金利や期間が当初想定と大きく異なる場合には、契約解除を認めた裁判例もあります。
相談背景
収益用の一棟アパートを購入予定の買主から、融資特約の設定に関する相談が寄せられました。
事前審査ではスムーズに承認が下りたものの、本審査では金利が上昇したり、借入期間が短縮されたりする可能性があるとのこと。
そのため、「想定より条件が厳しくなった場合にも契約を解除できるようにしたい」との要望が出ています。
仲介会社としても、融資条件の変更は実務上頻繁に起こるため、契約段階でどこまで解除事由として定められるか、過去の事例を踏まえて整理しておきたいという状況です。
弁護士の回答
1.金利・期間の変更でも解除が認められる場合がある
融資特約というと「融資が否認された場合に契約解除できる」という条項が一般的ですが、実際には「融資が承認されたものの、条件が想定より厳しくなった」ケースも少なくありません。
過去の裁判例では、地銀での融資を前提にしていたにもかかわらず、ノンバンクでしか融資が出ず、しかも金利が著しく高かった場合に「融資特約による解除を有効」と認めたものがあります。
このように、当初想定した条件と実際の条件とが大幅に乖離していれば、「融資非承認」と同視できるとして解除を認める考え方が存在します。
2.特約文言の明確化がトラブル防止の鍵
もっとも、「どの程度の条件差をもって解除できるのか」は、契約書の文言で大きく結果が変わります。
例えば、「金利が年1.0%以内、融資期間30年以上を条件とする」と明記しておけば、1.8%・25年返済などの条件であれば解除を主張しやすくなります。
一方、「金利等が当初予定と異なる場合」など、あいまいな表現だと、金利1.0%が1.05%になった程度では解除が認められない可能性もあります。
裁判所は「契約を維持できる余地がある限り、安易に解除を認めない」傾向があるため、数値的な基準を設けておくことが重要です。
3.仲介会社が留意すべき対応ポイント
融資条件の変更は、買主・金融機関の事情により日常的に発生します。
そのため、仲介会社としては、契約締結前にリスク共有を図り、買主・売主の双方に「どのような場合に解除できるか」を明確に伝えることが不可欠です。
特に収益物件では、金利上昇が収支計画や利回りに直結するため、買主側の不安も大きくなります。
契約書案を作成する段階で、融資特約の条文に「金利・期間の幅」を明記し、売主にもその意味を理解してもらうようにしましょう。
4.実務的に可能な対応策
実際の契約書では、次のような記載方法が有効です。
参考例:「買主は、融資金利が年1.5%を超える場合、または融資期間が20年未満となる場合には、本契約を解除することができる。」
このように数値化された条件であれば、後の判断が明確になり、トラブルを大幅に減らせます。
また、「軽微な変更(例:0.1%未満の金利差や数か月の期間短縮)は解除対象外」との注記を加えると、実務的な柔軟性を確保できます。
なお、金利は政策金利の変動に左右されるため、「契約時点の相場金利を基準」と明記しておくことも有効です。
5.まとめ
融資特約に「金利・期間の変更」を解除事由として盛り込むことは、実務的にも法的にも合理的です。
ただし、曖昧な表現では裁判所に認められにくく、逆に数値を明示した条項であれば、当事者双方にとって予測可能性の高い契約となります。
仲介会社としては、契約前の説明と書面化を徹底し、想定外の融資条件変更によるトラブルを未然に防ぐ姿勢が重要です。
弁護士の実務コメント
今回は、まず前提が「収益アパート」でスタートしている点もポイントです。
融資金利については、自宅・居住用の住宅ローンと、収益アパートのような投資用ローンとでは、金利水準が大きく異なるのが通常です。
収益アパートの場合、金利は物件の内容や契約者の属性、保有資産などによって大きく変動することが多い一方、住宅ローンは政策的に低金利に設定されており、その振れ幅は比較的小さい傾向にあります。
したがって、今回のように一定以上の金利でも融資特約を利用できるようにする場合には、前提となる物件の種類や想定される金利幅に応じて、特約内容を具体的に設計することが重要です。
また、融資特約については、金融機関の回答が曖昧であったり、融資特約を利用した解除を明確に通知したかどうかが争点となるケースも少なくありません。
そのため、融資結果の確認や、融資特約による解除を行うか否かについては、慎重に確認を行い、記録に残る形で相手方へ通知することが、後の紛争防止に極めて重要です。
収益物件の取引において、融資特約は単なる「融資の可否」だけでなく、「事業計画の成否」に関わる重要な条項であることが明確になりました。
契約段階で具体的な数値基準を設けておくことが、後のトラブル回避に直結する最大の防御策です。
契約は慎重に、説明は明確に。
今後も、不動産取引におけるリスク管理に役立つ情報を、お届けしてまいりますので、次回の連載にもご期待ください。

山村 暢彦氏
弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。
相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。
クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。
現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数7名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。
弁護士法人 山村法律事務所
神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階
電話番号 045-211-4275
神奈川県弁護士会 所属
山村法律事務所ウェブサイト
不動産・相続
企業法務